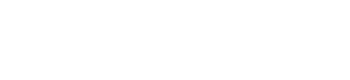研修医初期(無給副手)のころ、大学医局で信原先輩の手術助手をしたこともあり、誘われるままに、1974年の第1回肩関節研究会に参加しました。50年前でした。その後、研究会への参加を続けるうちに肩関節疾患に興味を持つようになりました。
一般に肩関節疾患の主訴は、肩が痛い、腕が上がらない、が二大兆候です。しかし、当初では、患者の肩を前にして、どのように診察を進めていけばよいのかわかりません。圧痛部位の特徴、肩関節の動きと疼痛との関係などを知らなければなりません。当たり前のことですが、肩疾患名を知ることです。同じ疾患の中にもその深い意味が隠されており、その区別を見出すには、臨床所見の特徴と画像所見をしっかりと見極めることが大切です。
そのうちに、外傷性肩関節不安定症と非外傷性肩関節不安定症との違いに興味を持つようになりました。反復性肩関節脱臼とLoose Shoulderが典型例ですが、当時の診断手段としては、臨床所見の特徴と関節造影が主です。造影手技が悪いと強い痛みを与えますし、微妙な関節唇陰影は判定できません。肩MRIが応用し始めましたが、今のように素晴らしい画像ではありません。客観的な診断に苦慮しました。
外傷性肩不安定症にはBankart lesionの修復(Bankart法手術)が合目的な手術です。肩関節鏡手術が導入し始めのころで一部の先生に限られており、一般に、大きく切開し展開する従来の観血的手術です。Bankart lesionは深部にあり、上腕骨頭を避けて広く展開することが難しく、狭い視野のなかで、糸を関節包にしっかりと修復するには困難を伴い、ときには長時間の手術時間を要しました。特殊な筋鈎やBankart用器具を種々考案されましたが、容易な手術術式ではありませんでした。そのためにPutti-Platt法やBristow法など手技の異なる方法が出現したのです。
次第に経験と報告を積み重ねて、肩関節医の仲間入りを許され、1991年に第18回日本肩関節研究会の会長を仰せつかりました。そのときに、日本肩関節学会に名称が変わりました。経緯は次のごとくです。そのころ内科をはじめ、多くの分野が細分化され、それぞれに学会名を表記するようになりました。研究会のままの名称では親睦会とみなされ、大きな学会場を確保できません。急遽、幹事会(現:理事会)に諮り、日本肩関節学会の名称を許され、総会で正式に承認されました。
同時に、そのころ世界を見渡しても、1977年以来18年間も肩関節研究会・学会を組織させ運営している国はありませんでした。アメリカ合衆国でさえ、American Shoulder & Elbow Surgeons(ASES)を1982年に設立したに過ぎません。DR. Neerが中心となって国際的な学会組織を設立し、その看板雑誌としてJournal of Shoulder&Elbow Surgery(JSES)を発刊したいとの機運がありました。第18回日本肩関節学会会長にも発刊に協力するよう要請があり、幹事会で編集委員会を立ち上げ、会長のわたしがそのままBoard of Trustees、International Editorial Boardの一員となりました。翌年1992年にJSESが発刊できました。
しかし、発刊した以上は多くの論文の提出が必要です。そこで、1977年の「雑誌肩関節」第1巻第1号以来発刊し素晴らしい内容を報告している日本肩関節学会に注目が集まりました。そのうちの和論文は英文論文となり、JSESの発展に貢献しています。もちろん二重投稿を厳重に注意して、Board of Trusteesに諮り、その検閲を得て国際編集委員会でaccept され、多くの論文が掲載されるようになりました。そのために、日本編集委員会だけの査読で、国際査読委員会をパスして掲載されるようになりました。しかし、現在では通常の国際雑誌に則り、厳しい査読を得て、多くの論文がJSESに掲載されており、喜ばしい限りです。